ハクビシンの侵入を防ぐ柵の選び方【目の細かいネットが◎】効果的な設置方法と、維持管理のコツを紹介

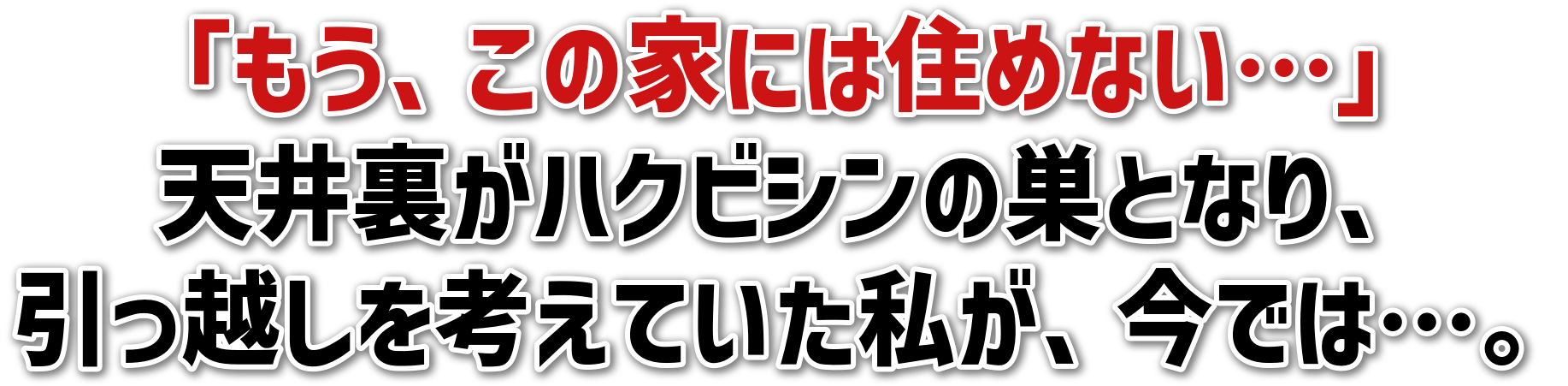
【この記事に書かれてあること】
ハクビシンの侵入に悩まされていませんか?- ハクビシンはわずか5cmの隙間から侵入可能
- 目の細かいネットが最も効果的な柵の素材
- 柵の高さは2メートル以上が理想的
- 金網フェンス・ネット柵・電気柵の特徴を比較
- 柵の下部の隙間をなくすことが重要
- 定期的なメンテナンスで長期的な効果を維持
適切な柵選びが、その解決の鍵を握っているんです。
でも、「どんな柵を選べばいいの?」って迷っちゃいますよね。
実は、ハクビシンはわずか5センチの隙間からでも侵入できるんです。
驚きですよね!
そこで今回は、ハクビシンの侵入を効果的に防ぐ柵の選び方と、その設置方法をご紹介します。
目の細かいネットから電気柵まで、それぞれの特徴を比較しながら、あなたの庭に最適な柵を見つけていきましょう。
さあ、「ハクビシンよ、さようなら!」と言える日はすぐそこです。
【もくじ】
ハクビシンの侵入を防ぐ柵選びの重要性

ハクビシンの侵入経路「5cmの隙間」に要注意!
ハクビシンは驚くほど小さな隙間から侵入できます。なんと、わずか5センチの隙間があれば、すいすいと入り込んでしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、本当なんです。
ハクビシンの体は柔らかくて、びっくりするほど柔軟性があります。
まるでゴムのように体を伸び縮みさせて、小さな隙間をすり抜けてしまうのです。
ですから、庭や畑を守るための柵を選ぶときは、この「5センチの法則」を忘れずに。
隙間が5センチ以上あるものは、ハクビシン対策としては全く役に立たないと言っても過言ではありません。
柵選びのポイントは3つあります。
- 隙間が5センチ未満であること
- 地面との間に隙間がないこと
- 柵の上部まで隙間がないこと
「地面との間に少し隙間があっても大丈夫だろう」なんて思っていませんか?
それが大間違い。
ハクビシンは地面を掘って潜り込むこともできるんです。
ですから、柵の下部はしっかりと地面に固定する必要があります。
柵の上部も要注意。
ハクビシンは木登りが得意で、柵の上から侵入することもあります。
上部まで隙間なく覆われた柵を選ぶか、上部に工夫を施す必要があるのです。
「5センチの隙間」、覚えておいてくださいね。
この小さな知識が、あなたの庭や畑を守る大きな力になるんです。
目の細かいネットが侵入防止に最適な理由
ハクビシン対策の柵選び、実は目の細かいネットが最適なんです。なぜって?
それには3つの理由があります。
まず第一に、隙間の小ささ。
目の細かいネットなら、ハクビシンが通り抜けられる5センチの隙間を作りません。
「キュッキュッ」とネットに顔を押し付けても、のっぽろぽろ?んと侵入できずに諦めるしかありません。
第二に、設置の簡単さ。
金網や板塀に比べて、ネットは軽くて扱いやすいんです。
「よいしょ」っと持ち上げて、「ピン!ピン!」と杭で固定するだけ。
特別な道具や技術がなくても、自分で設置できちゃいます。
そして第三に、コスト面。
目の細かいネットは、他の素材に比べてお財布に優しいんです。
「家計を圧迫せずに対策できる!」とホッとする方も多いはず。
ただし、注意点もあります。
- 耐久性が他の素材より劣る
- 強風で破れる可能性がある
- 見た目が他の素材より簡素
「ちょっと手間はかかるけど、その分お金は節約できる」というわけです。
目の細かいネットを使う時のコツは、地面との隙間をなくすこと。
ネットの下端を地面に埋め込むか、重しを置いて固定しましょう。
上部は内側に折り返すと、よじ登りを防止できますよ。
「見た目はシンプルだけど、効果は抜群!」それが目の細かいネットの魅力なんです。
あなたの大切な庭や畑を、このシンプルな守護者に任せてみませんか?
柵の設置場所「庭全体」を囲むのがベスト!
ハクビシン対策の柵、どこに設置すればいいの?答えは簡単。
庭全体を囲むのがベストなんです。
なぜ庭全体を囲う必要があるのでしょうか?
それは、ハクビシンが賢くて、隙があれば必ず侵入してくるからなんです。
「ここは守ったから大丈夫」なんて油断は禁物。
ちょっとした隙をみつけては、「よっこらしょ」と侵入してきちゃうんです。
庭全体を囲う際のポイントは3つ。
- 隙間なく連続させる
- 出入り口もしっかり対策
- 高さを統一する
確かに手間はかかりますが、それだけの価値は十分にあります。
例えば、一部分だけ柵を設置した場合を想像してみてください。
「ここは守られているから安心!」と思っても、ハクビシンは簡単に柵のない部分から侵入してきます。
まるで、鍵をかけ忘れた窓から泥棒が入ってくるようなものです。
「せっかく対策したのに...」と落胆するのは目に見えています。
一方、庭全体を囲えば、ハクビシンの侵入経路を完全に断つことができます。
「どこから入ろうかな?」とうろうろするハクビシンの姿が目に浮かびませんか?
結局、「ちぇっ、この家は無理だな」とあきらめて去っていくんです。
出入り口の対策も忘れずに。
開閉できるゲートを設置するか、取り外し可能な柵を使うのがおすすめです。
「人は通れるけど、ハクビシンは通れない」そんな賢い仕掛けを作りましょう。
庭全体を囲む柵、最初は大変に思えるかもしれません。
でも、一度設置してしまえば、あとは安心して庭を楽しめるんです。
「全部囲って正解だった!」そう思える日が、きっとすぐに来ますよ。
柵の高さ「2メートル以上」でハクビシン対策!
ハクビシン対策の柵、高さはどれくらいあればいいの?答えは2メートル以上です。
これだけの高さがあれば、ほとんどのハクビシンは飛び越えられません。
なぜ2メートル以上必要なのでしょうか?
それは、ハクビシンの驚くべき身体能力にあります。
この小さな動物、実はとてもアクロバティックなんです。
垂直に2メートル近くジャンプできるし、水平方向なら3メートル以上も飛べちゃうんです。
「えっ、そんなにすごいの?」と驚く方も多いはず。
でも、本当なんです。
ハクビシンは木登りの名人で、体が柔軟。
その能力を活かして、すごい高さまでよじ登ることができるんです。
2メートル以上の柵を設置する際のポイントは3つあります。
- 安定性を確保する
- 上部を内側に傾ける
- 滑りやすい素材を使う
高い柵は風の影響を受けやすいので、しっかりと地面に固定しましょう。
コンクリート基礎を作るのが理想的ですが、深く杭を打ち込むだけでも効果があります。
上部を内側に傾けるのは、ハクビシンのよじ登りを防ぐ秘策。
45度くらい傾けると、「うーん、登れない!」とハクビシンも諦めざるを得ません。
滑りやすい素材を使うのも効果的。
ツルツルの金属板や樹脂板を使えば、ハクビシンの爪がひっかからず、「すべー」っと滑り落ちちゃうんです。
「2メートルも高さがあったら、圧迫感がすごそう...」そう心配する方もいるでしょう。
確かに、見た目は重要です。
でも、植物を絡ませたり、デザイン性のある素材を使ったりすれば、見た目も良くなります。
「防犯対策しながら、おしゃれな庭になった!」なんて一石二鳥の効果も期待できますよ。
2メートル以上の高さ、覚えておいてくださいね。
この高さが、あなたの庭を守る「天の川」になるんです。
低すぎる柵はハクビシン対策に逆効果!
ハクビシン対策の柵、低すぎるのは大問題です。なんと、1メートル以下の柵はほとんど意味がないんです。
なぜ低い柵がダメなのか、理由は簡単。
ハクビシンにとっては、まるで「いらっしゃいませ?」と言っているようなものだからです。
この小さな侵入者、実は驚くほどの運動能力を持っています。
1メートルくらいの柵なんて、「よいしょっと」一瞬で飛び越えちゃうんです。
低い柵の危険性は3つあります。
- 簡単に乗り越えられる
- 侵入の足場になる
- 安心感を与えてしまう
「ピョンピョン」軽々と飛び越え、「あれ?こんなもので防げると思ったの?」とでも言わんばかりです。
さらに悪いことに、低い柵は侵入の足場にもなってしまいます。
柵を使って高い所に登り、そこから屋根や木に飛び移る。
「こんな方法があったか!」とハクビシンに新しい侵入ルートを教えてしまうんです。
そして最大の問題は、低い柵が人間に安心感を与えてしまうこと。
「柵を設置したから大丈夫」と油断してしまい、他の対策をおろそかにしがち。
結果、ハクビシンの被害がかえって増えてしまう...なんてことも。
「じゃあ、低い柵は全く意味がないの?」そんなことはありません。
低い柵でも、ネットと組み合わせたり、上部に工夫を加えたりすれば効果的になります。
例えば、柵の上にツルツルの板を斜めに取り付ければ、ハクビシンは登れなくなります。
大切なのは、「低い柵だけで満足しない」こと。
柵は高くするか、他の対策と組み合わせる。
それが、ハクビシンから庭を守る秘訣なんです。
「低すぎる柵は逆効果」、この言葉を胸に刻んでくださいね。
あなたの庭を守る最初の一歩は、この認識から始まるんです。
効果的な柵の種類と特徴を比較
金網フェンスvs電気柵!耐久性と効果を徹底比較
金網フェンスと電気柵、どっちがハクビシン対策に効果的?結論から言うと、効果は電気柵、耐久性は金網フェンスが勝っています。
まず金網フェンス。
これ、頑丈で長持ちするんです。
「一度設置したら、もう安心!」って感じ。
台風が来ても、びくともしません。
でも、ハクビシン対策としては少し弱点が。
「えっ、そうなの?」って思いますよね。
実は、ハクビシンって意外と器用。
金網をよじ登ったり、隙間を見つけて侵入したりするんです。
一方、電気柵はどうでしょう。
これ、ハクビシン対策としては抜群の効果があります。
ハクビシンが触れると、「ビリッ」っと軽い電気ショック。
一度経験すると、もう二度と近づかなくなるんです。
でも、耐久性では金網フェンスに及びません。
雨や雪の影響を受けやすいし、電源の管理も必要です。
ここで、両者の特徴をまとめてみましょう。
- 金網フェンス:耐久性◎、設置後の手間×、見た目○、効果△
- 電気柵:耐久性△、設置後の手間○、見た目×、効果◎
実は、両方の良いとこ取りができるんです。
金網フェンスを基本にして、上部に電気線を張る。
これなら耐久性も効果も抜群です。
ただし、注意点も。
電気柵は法律で設置に制限があるんです。
「え、そうなの?知らなかった!」って方も多いはず。
必ず事前に確認してくださいね。
結局のところ、どちらを選ぶかは状況次第。
でも、この比較を参考に、あなたの庭に最適な対策を見つけてくださいね。
ハクビシンに「ここには来られないよ?」って思わせる柵を作りましょう!
ネット柵vs金網フェンス!設置の手軽さを検証
ネット柵と金網フェンス、どっちが設置しやすい?結論から言うと、手軽さではネット柵が圧倒的に優位です。
ネット柵、これがね、すごく軽いんです。
「えっ、こんなに軽くて大丈夫?」って思うくらい。
でも、これが強みなんです。
一人でも「よいしょ」っと持ち上げて設置できちゃう。
道具もほとんど必要ありません。
杭を打って、ネットを張るだけ。
「休日の午後でサクッと終わっちゃった!」なんてことも。
一方、金網フェンスはどうでしょう。
これ、重いんです。
「うーん、重たい」って感じ。
一人で持ち上げるのは至難の業。
設置にも専門的な道具が必要になることが多いんです。
「休日つぶれちゃった...」なんてことも。
ここで、両者の設置の手軽さを比較してみましょう。
- ネット柵:重さ◎、必要な道具◎、作業時間◎、専門知識△
- 金網フェンス:重さ×、必要な道具×、作業時間×、専門知識○
「手軽さだけじゃ選べないよ」って思いますよね。
その通りです。
耐久性を考えると、実は金網フェンスの方が優れているんです。
ネット柵は風で破れたり、動物に噛み切られたりすることも。
「せっかく設置したのに...」なんて悲しい結末も。
じゃあ、どうすればいい?
実は、いいとこ取りの方法があるんです。
最初はネット柵で手軽に始めて、様子を見ながら徐々に金網フェンスに替えていく。
これなら、急場をしのぎつつ、長期的な対策もバッチリ。
ただし、注意点も。
ネット柵を選ぶなら、目の細かいものを。
ハクビシンは小さな隙間からも入り込んでしまうんです。
「え、そんな小さな隙間から?」って驚くかもしれませんが、本当なんです。
結局のところ、あなたの状況に合わせて選んでくださいね。
「今すぐ何とかしたい!」なら、ネット柵が大活躍。
「長期的な対策を」なら、金網フェンスがお勧めです。
どちらを選んでも、ハクビシンに「ここは入れないぞ」って思わせる柵を作りましょう!
電気柵vsネット柵!コスパと維持管理の違い
電気柵とネット柵、コスパと維持管理はどっちがいい?結論から言うと、初期コストと手軽さはネット柵、長期的な効果は電気柵が優れています。
まずネット柵。
これ、とにかく安いんです。
「えっ、こんなに安くていいの?」って思うくらい。
ホームセンターで気軽に買えて、設置も簡単。
「よし、今日から対策開始!」ってすぐに始められます。
維持管理も楽チン。
破れたら補修するくらいで、特別な手入れは必要ありません。
一方、電気柵はどうでしょう。
初期費用はネット柵より高めです。
「うわ、けっこうするんだ」って感じ。
設置にも少し手間がかかります。
でも、効果は抜群。
ハクビシンは一度電気ショックを経験すると、もう近づかなくなるんです。
ただし、維持管理には注意が必要。
電源の確認や、草刈りなどの定期的な手入れが欠かせません。
ここで、両者のコスパと維持管理を比較してみましょう。
- ネット柵:初期費用◎、設置の手軽さ◎、維持管理◎、長期的効果△
- 電気柵:初期費用×、設置の手軽さ△、維持管理×、長期的効果◎
実は、状況によって変わるんです。
広い農地を守るなら電気柵がお勧め。
小さな家庭菜園ならネット柵で十分かも。
でも、ちょっと待って。
実は、両方のいいとこ取りができるんです。
最初はネット柵で始めて、本当に被害が深刻なら電気柵に切り替える。
これなら、コストを抑えつつ、効果的な対策ができますよ。
ただし、注意点も。
電気柵は法律で設置に制限があるんです。
「え、そうなの?知らなかった!」って方も多いはず。
必ず事前に確認してくださいね。
結局のところ、あなたの状況と予算に合わせて選んでくださいね。
「とりあえず安く始めたい」ならネット柵、「確実に防ぎたい」なら電気柵がお勧めです。
どちらを選んでも、ハクビシンに「ここは諦めよう」って思わせる柵を作りましょう!
金属製vs樹脂製!耐久性と見た目の違いに注目
金属製と樹脂製の柵、どっちがいい?結論から言うと、耐久性は金属製、見た目は樹脂製が優れています。
まず金属製の柵。
これ、とにかく頑丈なんです。
「台風が来ても、びくともしない!」ってくらい。
長年使っても、形が崩れることはありません。
ただし、見た目はちょっと無機質。
「うーん、庭の雰囲気が変わっちゃうな」って感じることも。
一方、樹脂製の柵はどうでしょう。
見た目がとってもきれい。
「わぁ、おしゃれ!」って思わず声が出ちゃうくらい。
色や形も豊富で、庭の雰囲気に合わせやすいんです。
でも、耐久性では金属製に及びません。
強い衝撃で割れたり、長年の日光で劣化したりすることも。
ここで、両者の特徴をまとめてみましょう。
- 金属製:耐久性◎、重さ×、錆び△、見た目△、価格×
- 樹脂製:耐久性△、重さ◎、錆び◎、見た目◎、価格○
実は、使う場所によって変わるんです。
庭の目立つところには樹脂製、裏庭や畑には金属製。
こんな風に使い分けるのがコツです。
でも、ちょっと待って。
実は、両方の良いとこ取りができる商品もあるんです。
金属製の骨組みに樹脂製のカバーをつけたもの。
これなら耐久性も見た目も抜群ですよ。
ただし、注意点も。
どちらの素材でも、ハクビシン対策には目の細かさが重要。
「え、そんなに細かくなくても大丈夫でしょ?」って思うかもしれませんが、ハクビシンは小さな隙間からも入り込んでしまうんです。
結局のところ、あなたの庭の雰囲気と予算に合わせて選んでくださいね。
「長く使いたい」なら金属製、「見た目重視」なら樹脂製がお勧めです。
どちらを選んでも、ハクビシンに「この庭には入れないな」って思わせる柵を作りましょう!
ハクビシン対策柵の設置とメンテナンス方法

柵の下部「隙間ゼロ」にする簡単テクニック!
柵の下部の隙間をなくすことは、ハクビシン対策の要です。なぜなら、ハクビシンはわずか5センチの隙間からでも侵入できてしまうんです。
「え?そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、本当なんです。
ハクビシンの体は柔らかくて、まるでゴムのように伸び縮みするんです。
だから、ちょっとした隙間があれば「よいしょ」っと簡単に潜り込んでしまいます。
では、どうやって隙間をなくすのか?
簡単なテクニックをご紹介しましょう。
- 柵の下部を地面に埋める
- コンクリートの土台を作る
- L字型の金網を地面に這わせる
- 重石を置く
柵の下部から地面に向かって30センチほど金網を這わせます。
そして、その上に土や砂利をかぶせるんです。
これで、ハクビシンが地面を掘って侵入しようとしても、「あれ?掘れない!」とお手上げになっちゃいます。
もし、既に設置済みの柵がある場合は、隙間にコンクリートを流し込むのも効果的。
「ガチガチに固めちゃえ!」という感じです。
ただし、注意点も。
柵の下部を完全に塞ぐと、雨水がたまりやすくなることも。
適度な排水口を設けるのを忘れずに。
「せっかく隙間をなくしたのに、水浸しになっちゃった...」なんて悲しいことにならないようにしましょう。
隙間ゼロの柵で、ハクビシンに「ここは通れないよ?」って思わせちゃいましょう!
柵の上部を内側に45度傾斜させる効果とは
柵の上部を内側に45度傾斜させると、ハクビシンの侵入をぐっと防げるんです。なぜって?
ハクビシンのよじ登り能力を無効化できるからなんです。
ハクビシン、実はすごい登り上手なんです。
垂直の柵なら、「よいしょ」っと簡単によじ登っちゃう。
「えっ、そんなに器用なの?」って驚く方も多いはず。
でも、本当なんです。
木登りの名人ですからね。
ところが、柵の上部が45度傾いていると、話は別。
ハクビシンは「うーん、登れない!」ってお手上げになっちゃうんです。
なぜかというと、45度の角度だと、体重で引っ張られて落ちてしまうから。
「ズルズル?」っと滑り落ちちゃうわけです。
では、具体的にどうやって傾斜をつけるの?
方法は3つあります。
- 金網や板を45度に折り曲げる
- 別の部材を45度に取り付ける
- 傾斜のついた専用の柵を使う
金網や板を30センチほど内側に傾けて取り付けるだけ。
「これで完璧!」って感じです。
ただし、注意点も。
傾斜部分が短すぎると、ハクビシンが「えいっ」と飛び越えてしまうことも。
最低でも30センチ、できれば50センチくらいの長さがあると安心です。
また、傾斜部分の端がとがっていると、ケガの原因になることも。
端は丸めるか、カバーをつけるのを忘れずに。
この45度傾斜、見た目もおしゃれになるんですよ。
「防犯対策しながら、庭がスタイリッシュに!」なんて一石二鳥の効果も。
ハクビシンに「ここは諦めよう」って思わせる、賢い柵づくりをしましょう!
柵周辺に「滑りやすい素材」を設置するコツ
柵周辺に滑りやすい素材を設置すると、ハクビシンの侵入をさらに防げるんです。これ、ハクビシンの爪をすべらせる作戦なんです。
ハクビシン、爪がすごく発達しているんです。
普通の柵なら「ガリガリ」っと爪をひっかけて、するすると登ってきちゃう。
「えっ、そんなに器用なの?」って思いますよね。
でも、本当なんです。
ところが、滑りやすい素材があると、話は別。
ハクビシンは「あれ?登れない!」ってなっちゃうんです。
爪がひっかからないから、「ツルッ」って滑り落ちちゃうわけです。
じゃあ、具体的にどんな素材を使えばいいの?
おすすめは3つあります。
- なめらかな金属板
- ツルツルした樹脂板
- ガラス板
錆びにくくて長持ちするし、ツルツルで登りにくい。
「これは完璧!」って感じです。
設置する場所は、柵の上部と下部がポイント。
上部に付ければ、よじ登ってくるハクビシンを阻止できます。
下部に付ければ、地面から這い上がろうとするハクビシンを防げるんです。
ただし、注意点も。
滑りやすい素材は人間にとっても危険。
特に雨の日は滑りやすくなるので、触れる可能性がある場所には使わないようにしましょう。
「ハクビシン対策したけど、自分が滑って転んじゃった...」なんて悲しいことにならないように気をつけてくださいね。
また、見た目も考えましょう。
ピカピカの金属板だと、庭の雰囲気が台無しになることも。
樹脂板なら色を選べるので、庭に馴染みやすいですよ。
この滑りやすい素材、ハクビシンに「ここは無理だな?」って思わせる、賢い対策なんです。
ぜひ試してみてください!
定期点検で見逃しやすい「3つのポイント」
ハクビシン対策の柵、定期点検が大切なんです。でも、見逃しやすいポイントがあるんです。
今日は、その3つのポイントをご紹介します。
まず1つ目は、「地面との隙間」。
時間が経つと、地面が沈んだり、柵が浮いたりして、知らないうちに隙間ができちゃうんです。
「えっ、そんなことあるの?」って思うかもしれません。
でも、本当なんです。
わずか5センチの隙間でも、ハクビシンは「よいしょ」っと入り込んでしまうんです。
2つ目は、「ネジや金具の緩み」。
風や雨にさらされていると、少しずつ緩んでくるんです。
「ガタガタ」って音がしたら要注意。
ハクビシンに「ここ、弱そう!」って思われちゃいます。
3つ目は、「植物の絡まり」。
つる性の植物が柵に絡まると、ハクビシンの格好の足場になっちゃうんです。
「きれいだな?」って放っておいたら大変!
じゃあ、どうやって点検すればいいの?
ポイントは3つです。
- 月に1回は全体をチェック
- 雨の後は特に注意深く見る
- 夜間に懐中電灯で照らしてみる
懐中電灯で照らすと、昼間では見えない小さな隙間も「あれ?ここに穴が!」ってわかりやすいんです。
ただし、注意点も。
高所の点検は危険です。
はしごに登ったりするのは避けましょう。
「ハクビシン対策しようとして、自分がケガしちゃった...」なんて本末転倒ですからね。
定期点検、面倒くさいって思うかもしれません。
でも、「予防は治療に勝る」っていうでしょ?
点検を習慣にして、ハクビシンに「この家は守りが堅いな?」って思わせちゃいましょう!
季節別「柵のメンテナンス」重要ポイント
ハクビシン対策の柵、季節によってメンテナンスのポイントが変わるんです。今日は、季節別のメンテナンス重要ポイントをご紹介します。
まず春。
新芽の季節ですね。
実は、これがハクビシン対策の柵には大敵なんです。
「えっ、新芽が?」って思いますよね。
でも、本当なんです。
つる性の植物が柵に絡まると、ハクビシンの格好の足場になっちゃうんです。
だから、こまめに新芽を取り除くのがポイント。
夏は暑さ対策。
金属の柵は熱で膨張して、隙間ができやすくなるんです。
「ギシギシ」って音がしたら要注意。
ネジを締め直すのを忘れずに。
秋は落ち葉対策。
落ち葉が柵の下にたまると、そこから湿気が上がって柵を傷めちゃうんです。
「さらさら?」って音がする落ち葉、こまめに掃除しましょう。
冬は雪対策。
雪の重みで柵が歪んじゃうことがあるんです。
「えっ、そんなに重いの?」って驚くかもしれません。
でも、積もった雪はすごく重いんです。
こまめに雪下ろしをするのがポイントです。
では、季節別のメンテナンスポイントをまとめてみましょう。
- 春:新芽の除去、柵の清掃
- 夏:ネジの締め直し、日よけの設置
- 秋:落ち葉の掃除、さびのチェック
- 冬:雪下ろし、凍結による損傷チェック
急激な温度変化で、柵に歪みが出やすいんです。
「春が来た!」って喜ぶ前に、まずは柵のチェック。
これ、大切なポイントです。
ただし、危険な作業は避けましょう。
高所作業や重い雪の除去は、無理せず誰かに手伝ってもらうのがいいですよ。
「ハクビシン対策で自分がケガしては元も子もない」ですからね。
季節に合わせたメンテナンス、面倒くさいって思うかもしれません。
でも、「継続は力なり」っていうでしょ?
コツコツとケアすれば、ハクビシンに「この家は手ごわいな?」って思わせられるんです。
頑張りましょう!