ハクビシンのビニールハウス侵入対策【出入口の隙間がポイント】被害を防ぐ3つの方法と、内部での対策も解説

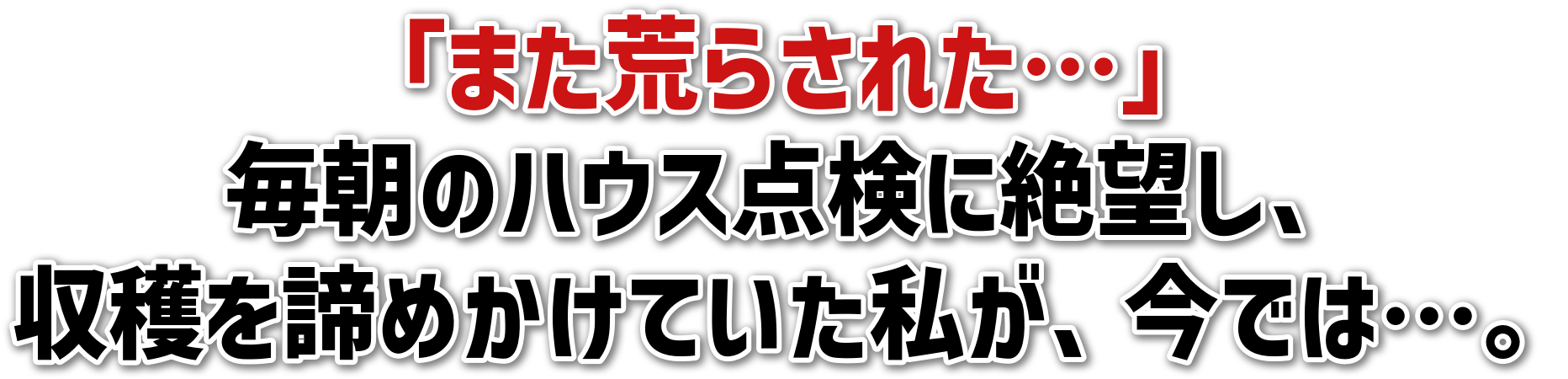
【この記事に書かれてあること】
ビニールハウスに忍び込むハクビシン、もう悩まされたくないですよね。- ハクビシンの侵入経路の9割は出入口の隙間
- 5cm以下の隙間でもハクビシンは侵入可能
- 出入口の完全密閉が最重要対策
- 換気口には金属製メッシュの設置が効果的
- ペットボトルの反射光やニンニクの匂いで撃退も
でも大丈夫。
たった5cmの隙間封じで、被害を劇的に減らせるんです。
ハクビシンの侵入経路の9割は出入口の隙間。
この弱点を知れば、対策は簡単です。
本記事では、出入口の完全密閉から換気口の保護まで、具体的な対策方法を紹介します。
さらに、ペットボトルの反射光やニンニクの匂いを使った意外な裏ワザも。
これを読めば、あなたのビニールハウスは安全な要塞に生まれ変わります。
さあ、ハクビシンとの知恵比べ、始めましょう!
ハクビシンのビニールハウス侵入被害の実態

ハクビシンが狙う「ビニールハウスの弱点」とは!
ビニールハウスの弱点は、柔らかい素材と隙間だらけの構造です。ハクビシンはこれらの弱点を見逃しません。
まず、ビニールハウスの素材自体が柔らかいのが大きな問題です。
ハクビシンは鋭い爪と歯を持っているので、ビニールを簡単に破ることができるんです。
「やった!簡単に入れそう」とハクビシンは喜んでいるかもしれません。
次に、ビニールハウスの構造にも弱点がたくさんあります。
例えば:
- 出入口の隙間
- 換気口の開口部
- ビニールの継ぎ目
- 地面との接点
「ここから入れそう」「あそこも狙えそう」と、ハクビシンは次々と侵入ポイントを見つけてしまうのです。
さらに、ビニールハウス内の環境もハクビシンを引き寄せる要因になっています。
温かくて、餌となる作物がたくさんあり、天敵から身を隠せる場所としても最適なんです。
「ここは天国だ!」とハクビシンは思っているかもしれません。
これらの弱点を知っておくことが、効果的な対策を立てる第一歩です。
ビニールハウスの構造をよく観察し、ハクビシンの目線で弱点を見つけることが大切です。
そうすることで、より効果的な防御策を講じることができるのです。
侵入経路の9割は「出入口の隙間」が原因
ビニールハウスへのハクビシン侵入、その9割は出入口の隙間が原因なんです。驚きますよね。
なぜ出入口がこんなにも危険なのでしょうか。
それは、出入口が人間にとって便利な構造になっているからです。
でも、その便利さがハクビシンにとっても都合が良いんです。
「ここなら簡単に入れそう」とハクビシンは考えています。
出入口の隙間が危険な理由は主に3つあります:
- 大きな開口部:人が出入りするため、必然的に大きな開口部ができてしまいます。
- 頻繁な開閉:作業のたびに開け閉めするので、完全に閉めるのを忘れがちです。
- 摩耗しやすい:頻繁に使うため、パッキンなどが劣化しやすく、隙間ができやすいのです。
「もう作業は終わったから、このくらいでいいか」と思って、ちょっとした隙間を放置してしまうことがあります。
でも、その小さな油断がハクビシンを招き入れる結果になってしまうんです。
対策としては、出入口の完全密閉が最も効果的です。
具体的には:
- 自動で閉まる扉の設置
- 二重扉の採用
- パッキンの定期的な点検と交換
- 夜間の施錠確認の徹底
「もう入れない!」とハクビシンを諦めさせることが、被害防止の第一歩なのです。
出入口の管理は面倒くさいと感じるかもしれません。
でも、毎日の小さな努力が、大きな被害を防ぐことにつながるんです。
ビニールハウスを守る、その鍵は私たちの手の中にあるのです。
ハクビシンが侵入できる「最小の隙間」は要注意
ハクビシンが侵入できる最小の隙間、それはわずか5センチなんです。信じられないかもしれませんが、本当なんです。
ハクビシンの体は意外と柔らかくて、くねくねと動きます。
「ここから入れるかな?」と、ハクビシンは細い隙間を見つけると試してみるんです。
そして、頭が通れば体も通れてしまうんです。
では、なぜハクビシンはこんなに小さな隙間から入れるのでしょうか。
その秘密は、ハクビシンの体の特徴にあります:
- 細長い体型:体が細長いので、隙間に合わせて体を伸ばせます。
- 柔軟な骨格:骨格が柔らかいので、体を曲げたり縮めたりできるんです。
- 滑らかな毛並み:毛が滑らかなので、引っかかりにくいんです。
- 強い前肢:力強い前足で体を引っ張り込むことができます。
「えっ、ここから入れるの?」と驚くような場所からも、スルスルっと入ってきてしまいます。
そのため、ビニールハウスの防御策を考える時は、「5センチルール」を覚えておくといいでしょう。
つまり、5センチ以上の隙間は全て危険だと考えるのです。
具体的な対策としては:
- 定期的な点検:小さな隙間も見逃さないよう、こまめにチェックします。
- 補修材の準備:小さな穴や隙間をすぐに塞げるよう、補修材を常備しておきます。
- 隙間テープの活用:ドアや窓の隙間には、専用のテープを貼ります。
- 金網の設置:換気口など、空けておく必要がある場所には細かい金網を取り付けます。
小さな隙間も侵入口になり得ると心に留めておけば、より効果的な防御ができるはずです。
ハクビシンの侵入を防ぐ、その鍵は細部への注意にあるのです。
侵入の証拠!「ハクビシンの痕跡」を見逃すな
ハクビシンが侵入した証拠、それは意外と身近なところに隠れています。これらの痕跡を見逃さないことが、早期発見・早期対策の鍵となるんです。
まず、目につきやすい痕跡から見ていきましょう:
- 足跡:泥や砂の上に、犬のような5本指の足跡が残ります。
- 糞:円筒形で直径2cm程度、黒っぽい色をしています。
- 毛:灰色がかった茶色の毛が、侵入口付近に残っていることがあります。
- 噛み跡:ビニールや木材に、鋭い歯形が残ることがあります。
次に、少し見つけにくい痕跡もあります:
- 臭い:ハクビシン特有のムスク臭が漂うことがあります。
- 油脂のシミ:体の油が擦れて、侵入口に薄いシミができることも。
- 爪痕:壁や支柱に、細い引っかき傷が残ることがあります。
でも、「何か変だな」と感じたら、ハクビシンの可能性を疑ってみるのがいいでしょう。
そして、最も重要な痕跡が作物への被害です。
例えば:
- 果物のかじり跡
- 野菜の食べ残し
- 茎や葉の踏み荒らし
「やられた!」と思う前に、すぐに対策を講じることが大切です。
痕跡を見つけたら、次のステップに進みましょう:
- 侵入経路の特定
- 被害状況の確認
- 対策方法の検討
- 再発防止策の実施
小さな痕跡も見逃さず、早めの対策を心がけることが、ビニールハウスを守る最良の方法なのです。
見逃し厳禁!「作物被害」の種類と特徴
ハクビシンによる作物被害、その種類と特徴を知ることは、対策を立てる上で非常に重要です。見逃してはいけない被害のサインを、しっかり押さえておきましょう。
まず、果物への被害が最も多いです。
ハクビシンは甘いものが大好物なんです。
具体的には:
- イチゴ:完熟したものから食べられます。
かじり跡が特徴的。 - ブドウ:房ごと食べられることも。
残った粒には歯形が。 - トマト:赤く熟したものを好みます。
半分だけ食べられることも。 - スイカ:穴を開けて中身を食べます。
丸い穴が目印。
次に、野菜への被害も見逃せません:
- ナス:実をかじられます。
表面に歯形が残ります。 - キュウリ:先端から食べられることが多いです。
- トウモロコシ:皮をむいて実だけ食べます。
芯が残ります。 - サツマイモ:地中の芋を掘り起こして食べます。
掘り跡が特徴的。
さらに、意外な被害もあります:
- 苗の踏み荒らし:歩き回って苗を倒します。
- 茎や葉の食害:栄養分を求めて、植物全体を食べることも。
- 根菜類の掘り起こし:ニンジンやダイコンを掘り出して食べます。
でも、「何かおかしいな」と感じたら、ハクビシンを疑ってみる必要があります。
被害の特徴を知ることで、次のような対策が可能になります:
- 被害を受けやすい作物の周りに、重点的に防護ネットを張る。
- 熟した果物は早めに収穫する。
- 食べ残しや落果を放置しない。
- 夜間の見回りを強化する。
被害の種類と特徴をよく知り、早期発見・早期対策に努めることが、ビニールハウスの作物を守る最善の方法なのです。
常に警戒心を持ち、小さな変化も見逃さない心構えが大切です。
ビニールハウスを守る効果的な対策方法
出入口の「完全密閉」が最重要ポイント
ビニールハウスの出入口を完全に密閉することが、ハクビシン対策の要です。ここをしっかり守れば、侵入の9割を防げるんです。
まず、出入口の扉をしっかりと閉めることが大切です。
「ちょっとだけ開けておいても大丈夫」なんて考えは禁物です。
ハクビシンは小さな隙間も見逃しません。
具体的な対策として、以下のポイントに注目しましょう:
- 自動で閉まる扉の設置
- 隙間テープの活用
- 扉の下部にブラシ付きの隙間埋めを取り付け
- 二重扉の導入
うっかり開けっ放しにしてしまう心配がなくなります。
「もう忘れちゃった!」なんてことがなくなるんです。
隙間テープは、扉の周りの小さな隙間を埋めるのに効果的です。
ぴったりと密着させて、ハクビシンの侵入口をふさぎます。
扉の下部にブラシ付きの隙間埋めを取り付けると、地面との隙間もしっかり塞げます。
これで、下からの侵入も防げるんです。
二重扉を導入すれば、さらに安心です。
一つ目の扉を開けても、もう一つの扉が守ってくれます。
まるで要塞のようですね。
ただし、注意点もあります。
あまりにも密閉しすぎると、ハウス内の温度や湿度の管理が難しくなることも。
換気にも気を配りながら、バランスの取れた対策を心がけましょう。
こうした対策を組み合わせることで、ハクビシンの侵入をぐっと減らすことができます。
出入口をしっかり守れば、安心して栽培に専念できるはずです。
ビニールの破れvs隙間!どちらが危険?
ビニールの破れと隙間、どちらもハクビシンの侵入口になりますが、実は隙間のほうがより危険なんです。なぜかというと、ハクビシンは自分で新たに穴を開けるよりも、既にある隙間を利用する傾向が強いからです。
「楽して入れる場所はないかな~」とハクビシンは考えているんです。
ただし、ビニールの破れも油断は禁物です。
小さな破れでも、ハクビシンがそこから爪を引っ掛けて広げてしまう可能性があります。
ですので、両方の対策が必要になってきます。
では、具体的にどう対策すればいいのでしょうか?
- 隙間対策:
- 定期的な点検
- 隙間テープの活用
- 隙間埋め材の使用
- 破れ対策:
- 専用の補修テープを使用
- 大きな破れは新しいビニールに交換
- 破れやすい場所を補強
「こんな小さな隙間、大丈夫だろう」なんて油断は禁物。
ハクビシンは5センチほどの隙間からでも入れてしまうんです。
破れ対策では、補修テープを内側と外側の両方から貼ると効果的です。
まるでサンドイッチのように、破れた部分を挟み込むイメージですね。
また、破れやすい場所には予めネットや補強用のテープを貼っておくのもいいでしょう。
「転ばぬ先の杖」というやつです。
こうした対策を行うことで、ハクビシンの侵入リスクをぐっと下げることができます。
小まめなチェックと素早い対応が、ビニールハウスを守る鍵になるんです。
換気口からの侵入を防ぐ「ワザ」を伝授
換気口からのハクビシン侵入、実はこれが意外と多いんです。でも、ちょっとした工夫で防ぐことができます。
まず大切なのは、目の細かい金属製メッシュを使うことです。
なぜ金属かというと、ハクビシンは鋭い歯を持っているので、プラスチック製のメッシュだとかじられてしまう可能性があるからです。
「ガリガリ」と音を立てて、あっという間に穴を開けられちゃうんです。
具体的な対策方法をいくつか紹介しましょう:
- 換気口全体を金属製メッシュで覆う
- 換気扇の外側にメッシュカバーを取り付ける
- 天窓には自動開閉装置を設置する
- 換気口の周りに忌避剤を散布する
ハクビシンは意外と小さな隙間から入り込めるので、1センチ四方以下の目の細かいものを選びましょう。
換気扇のメッシュカバーは、羽根が回転しても接触しない構造のものを選びます。
そうしないと、「ガタガタ」という不快な音が発生したり、最悪の場合、換気扇が壊れてしまったりします。
天窓の自動開閉装置は、使用時以外は確実に閉じておくために有効です。
「閉め忘れた!」なんてことがなくなりますよ。
忌避剤は、ハクビシンの嫌いな香りのものを選びましょう。
例えば、唐辛子スプレーや市販の動物忌避剤などが効果的です。
ただし、定期的に塗り直す必要があるので、少し手間がかかります。
これらの対策を組み合わせることで、換気口からのハクビシン侵入をぐっと減らすことができます。
「もう入れない!」とハクビシンに思わせることが大切なんです。
基礎部分の補強で「地中からの侵入」を阻止
ハクビシンは意外と器用で、地面から掘り進んでビニールハウスに侵入することもあるんです。でも、基礎部分をしっかり補強すれば、この侵入ルートを完全に断つことができます。
まず、最も効果的な方法はコンクリート基礎を作ることです。
地面から30センチほどの深さまでコンクリートを打ち、ハクビシンの掘り進みを物理的に阻止します。
「これじゃあ掘れないや」とハクビシンも諦めざるを得ません。
具体的な補強方法をいくつか紹介しましょう:
- コンクリート基礎の設置
- ブロック塀の設置
- 金属製の防護板の埋め込み
- 地中に金網を敷設
地面に接する部分をしっかり固定し、隙間ができないように注意しましょう。
金属製の防護板を地中に埋め込むのも効果的です。
地面から50センチほどの深さまで埋め込むと、ハクビシンの掘り進みを防ぐことができます。
地中に金網を敷設する方法もあります。
ビニールハウスの周囲1メートルほどの範囲に、目の細かい金網を地中に敷き詰めます。
これにより、ハクビシンが掘り進もうとしても、すぐに金網に当たってしまうんです。
ただし、注意点もあります。
基礎を作ることで、ビニールハウス内の排水が悪くなる可能性があります。
「水はけが悪くなっちゃった!」なんてことにならないよう、適切な排水対策も忘れずに行いましょう。
こうした基礎部分の補強により、地中からのハクビシン侵入を防ぐことができます。
「ここからは絶対に入れない」という要塞のような守りを作り上げることが、ビニールハウスを守る重要なポイントなんです。
侵入を許してしまったら?「内部対策」も重要
万が一、ハクビシンがビニールハウス内に侵入してしまった場合でも、慌てることはありません。内部での対策を講じることで、被害を最小限に抑えることができるんです。
まず重要なのは、ハクビシンを怖がらせることです。
ハクビシンは基本的に臆病な動物なので、驚かせることで追い払うことができます。
具体的な内部対策をいくつか紹介しましょう:
- センサー付きライトの設置
- 超音波発生装置の利用
- ラジオなどの音源の設置
- 作物の保護ネットの設置
- 餌となるものの撤去
「うわっ、まぶしい!」とハクビシンも逃げ出してしまうでしょう。
超音波発生装置は、人間には聞こえない高周波音を発生させ、ハクビシンを不快にさせます。
ただし、効果には個体差があるので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
ラジオなどの音源を設置するのも効果的です。
人の声や音楽が聞こえると、ハクビシンは人がいると勘違いして近づかなくなります。
作物を直接守るため、重要な作物の周りに小型のネットを張るのも良いでしょう。
「せっかく入ったのに食べられない!」とハクビシンも諦めざるを得ません。
そして、落果や傷んだ野菜などの餌となるものは、すぐに片付けることが大切です。
餌場化してしまうと、ハクビシンが何度も戻ってくる原因になってしまいます。
これらの対策を組み合わせることで、たとえハクビシンが侵入しても、被害を最小限に抑えることができます。
「ここは危険だ!」とハクビシンに思わせることが、内部対策の鍵なんです。
ハクビシン対策の裏ワザと長期的な解決策
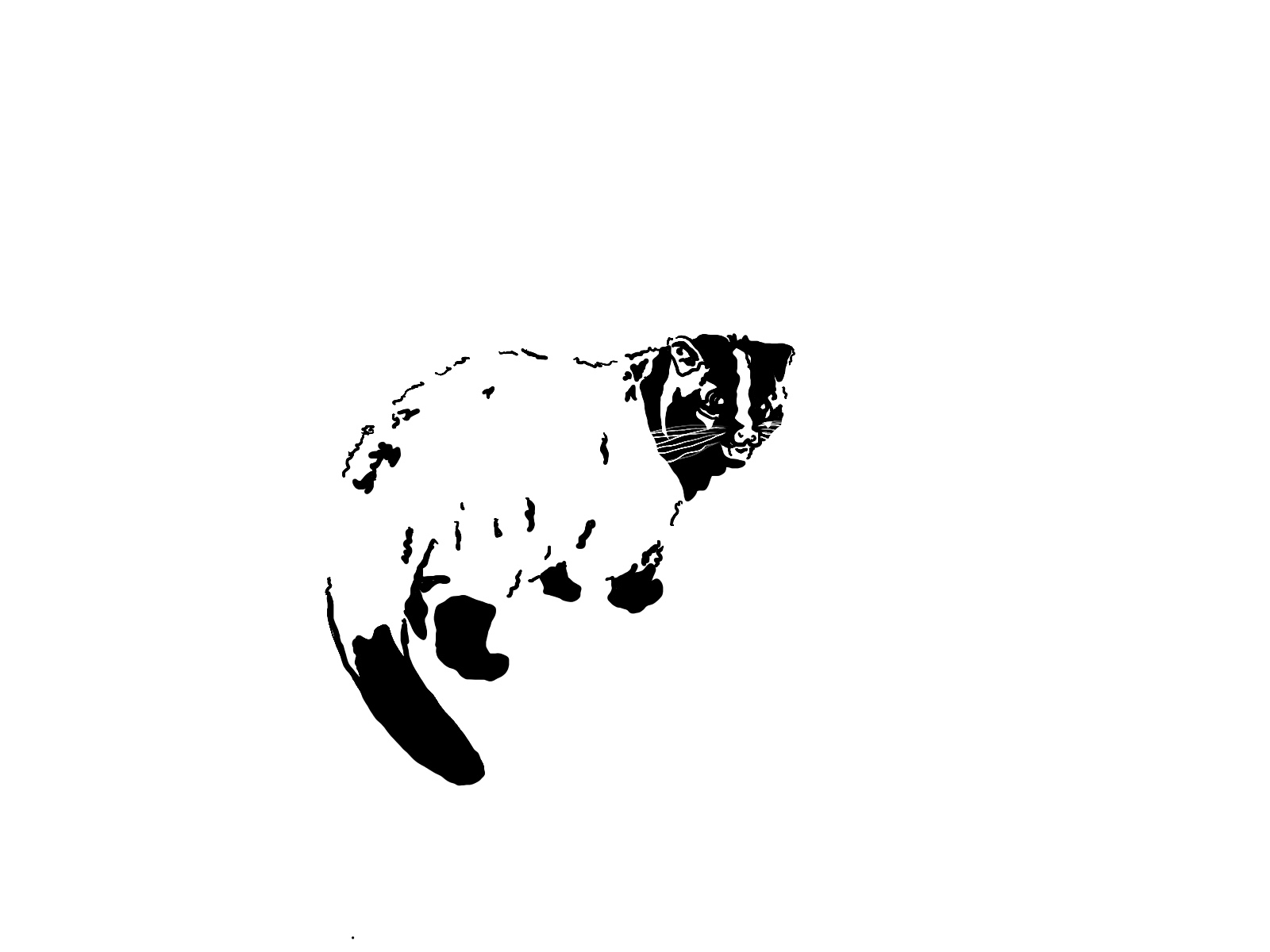
意外と効く!「ペットボトルの反射光」作戦
ペットボトルの反射光でハクビシンを撃退できるんです。これ、意外と効果絶大なんですよ。
まず、なぜペットボトルが効くのか、その仕組みから見ていきましょう。
ハクビシンは夜行性で、目が光に敏感なんです。
突然の光の動きに驚いて、「うわっ、何かいる!」と思って逃げちゃうんですね。
具体的な作り方はこんな感じです:
- 透明なペットボトルを用意する
- 中に水を半分ほど入れる
- ビニールハウスの周りに吊るす
これだけなんです。
風で揺れると、中の水が動いて光を反射します。
キラキラっと不規則に光るので、ハクビシンはびっくりしちゃうんです。
でも、注意点もあります。
ペットボトルの数は多ければ多いほど良いというわけではありません。
あまり多すぎると、ハクビシンが慣れてしまう可能性があるんです。
「あ、またあの光か」って感じで。
だいたい5メートルに1本くらいの間隔で設置するのがちょうどいいでしょう。
また、定期的に位置を変えるのもポイントです。
同じ場所だとハクビシンも学習しちゃうので、「今日はどこにあるかな?」とドキドキさせるわけです。
この方法、コストもほとんどかからないし、環境にも優しいんです。
「こんな簡単なことで効果があるの?」と思うかもしれませんが、実際にやってみると驚くほど効果があるんですよ。
ぜひ試してみてください。
匂いで撃退!「ニンニク」の驚きの効果
ニンニクの強烈な匂いでハクビシンを撃退できるんです。意外でしょう?
でも、これがなかなか効果的なんですよ。
ハクビシンは嗅覚が鋭敏なんです。
特に、ニンニクの強烈な香りは苦手みたい。
「うわっ、くさい!」って感じでしょうか。
この特性を利用して、ビニールハウスへの侵入を防ぐことができるんです。
具体的な使い方はこんな感じです:
- ニンニクをすりおろして、水で薄める
- スプレーボトルに入れて、ハウスの周りに散布
- ニンニクの球根をそのまま植える
- ニンニクオイルを染み込ませた布を吊るす
ハクビシンにとっては、まるで「くさいゾーン」みたいなものができちゃうんです。
でも、気をつけたいポイントもあります。
ニンニクの匂いは時間が経つと弱くなるので、定期的に補充する必要があります。
「もう大丈夫かな」って油断しちゃダメですよ。
また、あまりに強烈な匂いだと、近所の方に迷惑がかかる可能性もあります。
「何だか最近、ニンニク臭いな」なんて言われちゃうかも。
適度な濃度で使うことが大切です。
ニンニクには害虫を寄せ付けない効果もあるので、一石二鳥なんです。
しかも、栽培している作物に悪影響を与えることもありません。
「こんな身近なもので対策できるなんて!」って感じですよね。
台所にあるものでハクビシン対策ができるなんて、びっくりです。
ぜひ試してみてください。
効果にきっと驚くはずですよ。
音と動きで威嚇!「手作り風車」の威力
手作り風車でハクビシンを撃退できるんです。これ、意外と効果があるんですよ。
音と動きでハクビシンを怖がらせる作戦なんです。
ハクビシンは、突然の音や動きに敏感なんです。
「うわっ、何か動いてる!」って感じで警戒心を抱くわけです。
この特性を利用して、ビニールハウスへの侵入を防ぐことができるんです。
具体的な作り方はこんな感じです:
- ペットボトルを用意する
- ボトルの側面を細長く切り取って羽根を作る
- 中心に穴を開けて、竹ひごや針金を通す
- ビニールハウスの周りに設置する
これだけなんです。
風が吹くと、クルクルと回り始めます。
同時に、「カラカラ」という音も鳴るんです。
この予期せぬ動きと音がハクビシンを驚かせるんです。
ポイントは、風車をたくさん作ることです。
ビニールハウスの周りをぐるっと囲むように設置すると効果的です。
まるで「怖い音と動きのバリア」みたいなものができるんです。
でも、注意点もあります。
風が弱い日はあまり効果がないかもしれません。
そんな時は、風車と一緒に風鈴を吊るすのもいいでしょう。
「チリンチリン」という音が加わって、より効果的になります。
また、定期的にメンテナンスすることも大切です。
長く使っていると、回転が悪くなったり音が鳴らなくなったりすることがあります。
「もう効果ないかな」なんて思わずに、こまめにチェックしましょう。
この方法、材料費もほとんどかからないし、作るのも楽しいんです。
家族や友達と一緒に作れば、ハクビシン対策が楽しいイベントになっちゃいますよ。
「こんな簡単なものでハクビシンが来なくなるの?」って思うかもしれませんが、実際にやってみると効果にびっくりするはずです。
ぜひ試してみてください!
ハウス周辺の「環境整備」で根本から解決
ハウス周辺の環境を整備することで、ハクビシンの侵入を根本から防ぐことができるんです。これ、実は一番大切な対策なんですよ。
なぜ環境整備が効果的なのか、その理由を見ていきましょう。
ハクビシンは、餌と隠れ場所を求めてやってくるんです。
だから、これらを取り除けば、ハクビシンにとって魅力的な場所ではなくなるんです。
具体的な環境整備の方法をいくつか紹介します:
- 落果や生ごみをすぐに片付ける
- 草むらや藪を刈り込む
- ゴミ箱の蓋をしっかり閉める
- 不要な資材や道具を整理整頓する
- ハウス周辺に明るい照明を設置する
特に重要なのは、落果の管理です。
熟れた果実はハクビシンの大好物。
「おっ、おいしそう!」って寄ってきちゃうんです。
毎日ちゃんと拾い集めて、安全に処分しましょう。
草むらや藪の管理も大切です。
これらは、ハクビシンの絶好の隠れ場所になるんです。
「ここなら安全に休めるぞ」なんて思われちゃいます。
定期的に刈り込んで、隠れられないようにしましょう。
ゴミ箱の管理も忘れずに。
ハクビシンは食べ物の匂いに敏感なんです。
しっかり蓋を閉めて、匂いが漏れないようにしましょう。
照明の設置も効果的です。
ハクビシンは明るい場所を嫌うので、ハウス周辺を明るくすることで寄り付きにくくなります。
これらの対策、「面倒くさいな」って思うかもしれません。
でも、長期的に見ると、これが一番効果的で持続可能な方法なんです。
毎日少しずつ続けていけば、きっとハクビシンの被害は減っていきますよ。
根気強く続けてみてください。
持続可能な「長期的対策」で被害ゼロへ
持続可能な長期的対策を立てることで、ハクビシンの被害をゼロに近づけることができるんです。一時的な対策だけでなく、長期的な視点を持つことが大切なんですよ。
なぜ長期的対策が必要なのか、考えてみましょう。
ハクビシンは賢い動物で、短期的な対策にはすぐに慣れてしまうんです。
「あ、この光は怖くないな」「この音ももう大丈夫」って感じで。
だから、継続的に効果がある対策を立てる必要があるんです。
具体的な長期的対策をいくつか紹介します:
- 定期的な侵入経路のチェックと補修
- 季節に合わせた対策の見直し
- 地域ぐるみでの取り組み
- 生態系のバランスを考慮した対策
- 新しい技術や方法の情報収集と導入
ハクビシンは小さな隙間も見逃しません。
「ここから入れるぞ」って思われちゃいます。
定期的に点検して、見つけた隙間はすぐに塞ぎましょう。
季節による対策の見直しも重要です。
春と秋はハクビシンの繁殖期で、特に活発になります。
「赤ちゃんのために食べ物を探さなきゃ」って感じでしょうか。
この時期は特に注意が必要です。
地域ぐるみでの取り組みも効果的です。
隣の畑では対策をしていないのに、自分の畑だけ対策しても意味がありません。
「隣はおいしそうだな」ってハクビシンに思われちゃいます。
近所の人と協力して、広い範囲で対策を行いましょう。
生態系のバランスを考えることも大切です。
ハクビシンの天敵を増やすことで、自然なバランスを取ることができます。
例えば、フクロウの巣箱を設置するのも一つの方法です。
新しい技術や方法にも注目しましょう。
ハクビシン対策の研究は日々進んでいます。
「こんな方法があったんだ!」って驚くような新しい対策方法が見つかるかもしれません。
これらの対策、一朝一夕には効果が出ないかもしれません。
「効果ないじゃん」って思うこともあるでしょう。
でも、諦めずに続けることが大切なんです。
長期的に見れば、必ず効果は現れます。
根気強く続けていけば、きっとハクビシンとの平和な共存が実現できるはずです。
頑張ってみてくださいね!